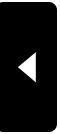2018年04月02日
NASの交換
我々工務店では、見積書や請求書といった事務に必要な書類を始め、図面データ、それに写真データが業務を行うために必要です。
当社では、業務で使用するこれらのデータをNAS(ネットワークHDD)に保管しております。
NASは社内のPCどこからでもアクセスできるようになっていてとても便利ですが、ハードディスクという機械的に動く機器ですので、突然の故障には備えないといけません。そこで、RAIDという仕組みを使って、万一の故障に備えておりました。
先日、PCにエラーメッセージが出てくるので、何かと思い、NAS本体を見ると、赤いインジケータが光っているのを見つけました。

Buffalo社のLS-WXLという機種です。
RAIDにもいくつか種類があって、このNASはRAID 1で使用していました。それに、外付けのUSB接続のHDDを取り付けて、定期的にバックアップを取るという2重の対策を行っていました。
RAID 1というのはNASに内蔵されている2台のHDDに同時の同じ内容を書き込み、片方のHDDが故障しても、もう片方のHDDが生きていればデータが保存されているというものです。NASの設定画面を辿っていくと、このHDDのうち1台が故障して、「デグレモード」になっているとのことです。
ここで、故障したHDDを交換すればよいのですが、万が一、交換中に生き残っているほうのHDDが故障してしまったらデータがすべてなくなるという恐ろしい事態になります。そこで、まずは、外付けのUSB HDDにバックアップを取りました。
また、NAS自体も3年目に突入しており、HDDの他に、それをコントロールする回路が故障する可能性もあるということで、奮発して新たなNASを導入しました。今回はメーカーを変えて、Synology社のDS416jという機種にしました。このNASは4台のHDDを内蔵でき、それぞれに分散して同じデータを書き込むので、4台のうち2台の故障まで対応できるとのことです。(RAID6相当)
また、内蔵するHDDもNAS対応の長寿命タイプにしました。
このNASは説明書などが少なく、設定するのがとても不安でした。しかし、終わってしまえば、なんとかなってしまった、という感じです。経緯を写真で記録しておきます。(自分の備忘録も兼ねて)

こんな梱包で到着しました。

梱包を開封して、NAS本体を開けていきます。

こちらが内蔵するHDD。NAS対応の少し高価なものです。奮発しちゃった!

全部で4台あります。

トレイにHDDをセットし、それをNAS本体に差し込みます。
これで蓋を閉めます。その後、設置場所に置いて、LANケーブル、電源ケーブルを接続します。

送られてきた梱包にはマニュアルの類がほとんど入っていないので、ネットからダウンロードすることになります。
この辺りで経費節減してコストダウンしているのですね。


NASには自動的にルーターからIPアドレスが付与されるのですが、それが何らかの拍子に動くとまずいので、付与されたIPアドレスは固定化してしまいました。
NASの操作はDISK STATION MANAGERから行います。Windows10を使用しているのですが、ブラウザに直にIPアドレスを打つと、DISK STATION MANAGERが開きます。ここで各種設定やソフトのインストールもできます。この仕組みを理解するのに少し時間が掛かりましたが、慣れてしまえば、こんなものか、という感じでした。
ちなみに、今まで使っていたNASもHDDを交換しました。

全く同じHDDが手に入りました。

交換した後の様子
こちらもRAIDの復旧をやったら、あっさり元に戻りました。今度はこちらのNASをバックアップにします。
RAID6相当のNASにデータを保管して、それをRAID1のNASにバックアップする体制にしておけば、データの保管についてはほぼ大丈夫かな、と思います。
お客様の大事なデータ、大切に保管させていただきます。
(片桐秀夫)
当社では、業務で使用するこれらのデータをNAS(ネットワークHDD)に保管しております。
NASは社内のPCどこからでもアクセスできるようになっていてとても便利ですが、ハードディスクという機械的に動く機器ですので、突然の故障には備えないといけません。そこで、RAIDという仕組みを使って、万一の故障に備えておりました。
先日、PCにエラーメッセージが出てくるので、何かと思い、NAS本体を見ると、赤いインジケータが光っているのを見つけました。
Buffalo社のLS-WXLという機種です。
RAIDにもいくつか種類があって、このNASはRAID 1で使用していました。それに、外付けのUSB接続のHDDを取り付けて、定期的にバックアップを取るという2重の対策を行っていました。
RAID 1というのはNASに内蔵されている2台のHDDに同時の同じ内容を書き込み、片方のHDDが故障しても、もう片方のHDDが生きていればデータが保存されているというものです。NASの設定画面を辿っていくと、このHDDのうち1台が故障して、「デグレモード」になっているとのことです。
ここで、故障したHDDを交換すればよいのですが、万が一、交換中に生き残っているほうのHDDが故障してしまったらデータがすべてなくなるという恐ろしい事態になります。そこで、まずは、外付けのUSB HDDにバックアップを取りました。
また、NAS自体も3年目に突入しており、HDDの他に、それをコントロールする回路が故障する可能性もあるということで、奮発して新たなNASを導入しました。今回はメーカーを変えて、Synology社のDS416jという機種にしました。このNASは4台のHDDを内蔵でき、それぞれに分散して同じデータを書き込むので、4台のうち2台の故障まで対応できるとのことです。(RAID6相当)
また、内蔵するHDDもNAS対応の長寿命タイプにしました。
このNASは説明書などが少なく、設定するのがとても不安でした。しかし、終わってしまえば、なんとかなってしまった、という感じです。経緯を写真で記録しておきます。(自分の備忘録も兼ねて)
こんな梱包で到着しました。
梱包を開封して、NAS本体を開けていきます。
こちらが内蔵するHDD。NAS対応の少し高価なものです。奮発しちゃった!
全部で4台あります。
トレイにHDDをセットし、それをNAS本体に差し込みます。
これで蓋を閉めます。その後、設置場所に置いて、LANケーブル、電源ケーブルを接続します。
送られてきた梱包にはマニュアルの類がほとんど入っていないので、ネットからダウンロードすることになります。
この辺りで経費節減してコストダウンしているのですね。
NASには自動的にルーターからIPアドレスが付与されるのですが、それが何らかの拍子に動くとまずいので、付与されたIPアドレスは固定化してしまいました。
NASの操作はDISK STATION MANAGERから行います。Windows10を使用しているのですが、ブラウザに直にIPアドレスを打つと、DISK STATION MANAGERが開きます。ここで各種設定やソフトのインストールもできます。この仕組みを理解するのに少し時間が掛かりましたが、慣れてしまえば、こんなものか、という感じでした。
ちなみに、今まで使っていたNASもHDDを交換しました。
全く同じHDDが手に入りました。
交換した後の様子
こちらもRAIDの復旧をやったら、あっさり元に戻りました。今度はこちらのNASをバックアップにします。
RAID6相当のNASにデータを保管して、それをRAID1のNASにバックアップする体制にしておけば、データの保管についてはほぼ大丈夫かな、と思います。
お客様の大事なデータ、大切に保管させていただきます。
(片桐秀夫)
タグ :NAS
2017年12月11日
耐震補強工事 現場見学会のお知らせ
耐震補強工事 現場見学会のお知らせ
このたび、築80年ほどの住宅のリフォーム工事を行いました。この住宅の現場見学会を開催しますのでお知らせします。

↑上記画像をクリックすると、PDFデータのダウンロードができます。
今回の耐震補強工事は、骨組を残しての大改造です。、建てなおした部分もあり、新築と遜色ない手間をかけています。
既存の部分は耐震改修工事を行い、仕上げ材も新しくしています。塗壁を多用し、ビニールクロスは使用していません。
増築部もあり、こちらは新築工事と同じように、骨組から作り直しています。
本日、足場が撤去されて、全容が露わになりました。

今日現在(12月11日)、まだ工事中のところもありますが、12月16日の見学会に向けて追い込みの工事を行っています。
興味のある方は、お気軽にお越しください。
(片桐秀夫)
このたび、築80年ほどの住宅のリフォーム工事を行いました。この住宅の現場見学会を開催しますのでお知らせします。

↑上記画像をクリックすると、PDFデータのダウンロードができます。
今回の耐震補強工事は、骨組を残しての大改造です。、建てなおした部分もあり、新築と遜色ない手間をかけています。
既存の部分は耐震改修工事を行い、仕上げ材も新しくしています。塗壁を多用し、ビニールクロスは使用していません。
増築部もあり、こちらは新築工事と同じように、骨組から作り直しています。
本日、足場が撤去されて、全容が露わになりました。
今日現在(12月11日)、まだ工事中のところもありますが、12月16日の見学会に向けて追い込みの工事を行っています。
興味のある方は、お気軽にお越しください。
(片桐秀夫)
2017年11月01日
ファイバーカメラを導入してみました
先日、季節外れともいえるような台風が2週連続で静岡近辺にやってきて、いくつかの痕跡を残していきました。
新聞には大きな被害について報道がなされますが、新聞には載らないような被害の連絡が急増します。それが雨漏れです。
当社では、自社で建築した建物の他、他社が既にメンテナンスをしていない建物、建築会社が廃業などですでに存在していないような建物のメンテナンスも引き受けることがあります。自社建築の建物なら資料も残っていますし、もしも雨漏れを起こしても、比較的対応がし易いです。(雨漏れ自体、あってはならないことですが。) しかし、他社施工の建物では、雨漏れの特定をするのが中々困難です。
屋上や屋根から水をかけ、天井裏を覗いて、どこから雨が侵入しているのか探ります。木造住宅のように天井裏に余裕があるならまだしも、陸屋根(平らな屋根)のビルなどでは、人間の体が入っていきこともできず、調査に苦労します。そもそも、天井裏にもぐれれば良い方で、天井裏に潜る点検口さえないこともしばしばです。
そこで、今回導入したのがファイバーカメラです。8mmほどのファイバーの先にカメラが取り付けられており、狭い処を撮影することができるそうです。通販サイトで、送料を入れても3,000円ほどでした。

ゆうぱっくに入れられて、こんな状態で到着しました。

開封したところです。ファイバーケーブルは5mあります。
日本語の説明書が同封されていましたが、コピーを何度か重ねたものなのか、文字は認識できるけれど、バーコードの読み取りは出来ませんでした。スマホに手入力で「moqo view」と入力し、Google Playよりアプリをダウンロードしました。アプリは無料です。
説明書通りに操作して、WiFiを設定。

ファイバーカメラの画像がスマホに転送できるのは確認できました。思ったよりも、画像は鮮明です。
さて、今日も早速雨漏れ改修の現場があります。早速、このカメラで点検してみましょう!
(片桐秀夫)
新聞には大きな被害について報道がなされますが、新聞には載らないような被害の連絡が急増します。それが雨漏れです。
当社では、自社で建築した建物の他、他社が既にメンテナンスをしていない建物、建築会社が廃業などですでに存在していないような建物のメンテナンスも引き受けることがあります。自社建築の建物なら資料も残っていますし、もしも雨漏れを起こしても、比較的対応がし易いです。(雨漏れ自体、あってはならないことですが。) しかし、他社施工の建物では、雨漏れの特定をするのが中々困難です。
屋上や屋根から水をかけ、天井裏を覗いて、どこから雨が侵入しているのか探ります。木造住宅のように天井裏に余裕があるならまだしも、陸屋根(平らな屋根)のビルなどでは、人間の体が入っていきこともできず、調査に苦労します。そもそも、天井裏にもぐれれば良い方で、天井裏に潜る点検口さえないこともしばしばです。
そこで、今回導入したのがファイバーカメラです。8mmほどのファイバーの先にカメラが取り付けられており、狭い処を撮影することができるそうです。通販サイトで、送料を入れても3,000円ほどでした。
ゆうぱっくに入れられて、こんな状態で到着しました。
開封したところです。ファイバーケーブルは5mあります。
日本語の説明書が同封されていましたが、コピーを何度か重ねたものなのか、文字は認識できるけれど、バーコードの読み取りは出来ませんでした。スマホに手入力で「moqo view」と入力し、Google Playよりアプリをダウンロードしました。アプリは無料です。
説明書通りに操作して、WiFiを設定。
ファイバーカメラの画像がスマホに転送できるのは確認できました。思ったよりも、画像は鮮明です。
さて、今日も早速雨漏れ改修の現場があります。早速、このカメラで点検してみましょう!
(片桐秀夫)
2017年09月01日
被災建築物応急危険度判定 模擬訓練参加
今日は9月1日、防災の日です。1923年のこの日に関東大震災が起こったので、この日が防災の日になったのですよね。
私は静岡県建築士会員として、静岡市が主催する被災建築物応急危険度判定の模擬訓練に参加してきました。
「応急危険度判定」とは、大地震が起きた時に、その建物がその後も引き続き使用できるかどうかの判定をするものです。その判定の結果、危険であれば赤色、要注意であれば黄色、問題なければ緑色のステッカーを建物に貼っていきます。
この判定は応急危険度判定士が行います。応急危険度判定士は、建築士資格を持ち、決められた講習を受けることでなることができます。私も一級建築士資格取得後、すぐに応急危険度判定の講習を受けました。

私自身はまだ実際の大地震での判定業務を行ったことはありませんが、このような訓練に時々参加して、判定の方法を忘れないようにしています。本日の訓練に備えて、昨晩、応急危険度判定士手帳を読み返しました。

赤(危険)、黄(要注意)、青(調査済=安全)の判定に大きな影響を与えるのが、建物がどれだけ傾いているか(=傾斜)です。傾きが少ない方が被災度が少ないということになります。
傾斜測定には下げ振りという測定器を使います。測定器と言っても原始的なもので、おもりの付いたひもをぶら下げて、根元の部分と先端の部分での離れの差を測定します。


1200mmの高さで、20mm以上の傾斜があれば要注意、60mm以上の傾斜があれば危険となります。
今回は、会社事務所近くの厚生病院とその近隣の住宅16軒の傾斜測定を訓練として行いました。実際の応急危険度判定には他にもいくつかの項目があるのですが、建物がどれだけ傾いているかが判定結果に及ぼす影響が大きいため、この部分のみを行おう、ということです。

静岡市の担当者、インターシップ生、応援市である藤枝市の担当者の方と4名で回りました。
今回は地震が起きたわけではないので、被災した建物があるわけではありません。しかし、傾斜測定をしてみると、やはり古い家の中には若干、傾斜のあるものもありました。かと言って、判定結果が黄色になるわけではなく、全ての家が青相当の傾斜に収まりました。
訓練に向かう前は、少し不安なこともありましたありました。しかし、訓練を終わってみれば、机上では気がつかなかったこともいろいろとありましたし、実際の判定業務の時の課題も見えてきました。1時間にも満たない訓練でしたが、私にとっては有意義な訓練だったと思います。
訓練終了後、会社事務所に戻ってから、アマチュア無線による通信訓練にも参加しました。これはアマチュア無線を使って、いろいろな情報を静岡市に集約するための通信訓練です。自宅にもアマチュア無線用のアンテナが設置してありますが、今回はあえて携帯型のハンディトランシーバーを使用して、静岡市が設置したアマチュア局と交信できるか試してみました。事務所の前の道路から呼び出してみたところ、無事つながり、応急危険度判定に参加してきたことを伝えました。

大地震、来ないのが一番ですが、来たらどうするのか、考えることができた防災の日となりました。
(片桐秀夫)
私は静岡県建築士会員として、静岡市が主催する被災建築物応急危険度判定の模擬訓練に参加してきました。
「応急危険度判定」とは、大地震が起きた時に、その建物がその後も引き続き使用できるかどうかの判定をするものです。その判定の結果、危険であれば赤色、要注意であれば黄色、問題なければ緑色のステッカーを建物に貼っていきます。
この判定は応急危険度判定士が行います。応急危険度判定士は、建築士資格を持ち、決められた講習を受けることでなることができます。私も一級建築士資格取得後、すぐに応急危険度判定の講習を受けました。
私自身はまだ実際の大地震での判定業務を行ったことはありませんが、このような訓練に時々参加して、判定の方法を忘れないようにしています。本日の訓練に備えて、昨晩、応急危険度判定士手帳を読み返しました。
赤(危険)、黄(要注意)、青(調査済=安全)の判定に大きな影響を与えるのが、建物がどれだけ傾いているか(=傾斜)です。傾きが少ない方が被災度が少ないということになります。
傾斜測定には下げ振りという測定器を使います。測定器と言っても原始的なもので、おもりの付いたひもをぶら下げて、根元の部分と先端の部分での離れの差を測定します。
1200mmの高さで、20mm以上の傾斜があれば要注意、60mm以上の傾斜があれば危険となります。
今回は、会社事務所近くの厚生病院とその近隣の住宅16軒の傾斜測定を訓練として行いました。実際の応急危険度判定には他にもいくつかの項目があるのですが、建物がどれだけ傾いているかが判定結果に及ぼす影響が大きいため、この部分のみを行おう、ということです。
静岡市の担当者、インターシップ生、応援市である藤枝市の担当者の方と4名で回りました。
今回は地震が起きたわけではないので、被災した建物があるわけではありません。しかし、傾斜測定をしてみると、やはり古い家の中には若干、傾斜のあるものもありました。かと言って、判定結果が黄色になるわけではなく、全ての家が青相当の傾斜に収まりました。
訓練に向かう前は、少し不安なこともありましたありました。しかし、訓練を終わってみれば、机上では気がつかなかったこともいろいろとありましたし、実際の判定業務の時の課題も見えてきました。1時間にも満たない訓練でしたが、私にとっては有意義な訓練だったと思います。
訓練終了後、会社事務所に戻ってから、アマチュア無線による通信訓練にも参加しました。これはアマチュア無線を使って、いろいろな情報を静岡市に集約するための通信訓練です。自宅にもアマチュア無線用のアンテナが設置してありますが、今回はあえて携帯型のハンディトランシーバーを使用して、静岡市が設置したアマチュア局と交信できるか試してみました。事務所の前の道路から呼び出してみたところ、無事つながり、応急危険度判定に参加してきたことを伝えました。
大地震、来ないのが一番ですが、来たらどうするのか、考えることができた防災の日となりました。
(片桐秀夫)
2017年08月20日
ショールームで打ち合わせ
本日は、お客様と共に「クリナップ静岡ショールーム」へ出向いて打合せをしてきました。
キッチンの交換の予定をされているお客様です。

当社では、メーカーの隔てなくお取り扱いさせていただいております。お客様の意向と予算に合ったメーカー、機種をご提案させていただいております。
キッチンも各メーカー取り扱っておりますが、個人的にイチオシなのは、クリナップのクリンレディです。フレームがステンレスで作られているため、丈夫で衛生的なのです。
今回もクリンレディの打ち合わせでした。予め現地を調査し、写真を撮影しました。これと図面などの情報をショールームの方と共有し、当日の打ち合わせに臨みます。お客様だけではなく、当社の担当者が同伴することで、実際の納まりや工事の時の注意点を頭に入れながら打ち合わせしますから、機種の選定に対して的確な情報提供ができます。結果、お望みのキッチンを選定できるという訳です。
システムキッチンはそれぞれのパーツの選択肢がたくさんあり、どれにしようか迷うことが多いのですが、ショールームにはキッチンのスペシャリストである説明員もおり、一つずつ説明を受けながら判断することができます。

↑打合せ途中で使用したミニチュアモデル
クリナップに限らず、他のメーカーのショールームも静岡市にはたくさんあります。新築、リフォームの際には、必ず、ショールームの見学をすべきです。私どもがそのお手伝いをさせていただければと思います。
なお、当社はクリナップの「水まわり工房」登録店です。

ショールームを使ったフェアを行うこともあります。その時期が来ましたら、また、お知らせします。
クリナップ「水まわり工房」のホームページへリンク
(片桐秀夫)
キッチンの交換の予定をされているお客様です。
当社では、メーカーの隔てなくお取り扱いさせていただいております。お客様の意向と予算に合ったメーカー、機種をご提案させていただいております。
キッチンも各メーカー取り扱っておりますが、個人的にイチオシなのは、クリナップのクリンレディです。フレームがステンレスで作られているため、丈夫で衛生的なのです。
今回もクリンレディの打ち合わせでした。予め現地を調査し、写真を撮影しました。これと図面などの情報をショールームの方と共有し、当日の打ち合わせに臨みます。お客様だけではなく、当社の担当者が同伴することで、実際の納まりや工事の時の注意点を頭に入れながら打ち合わせしますから、機種の選定に対して的確な情報提供ができます。結果、お望みのキッチンを選定できるという訳です。
システムキッチンはそれぞれのパーツの選択肢がたくさんあり、どれにしようか迷うことが多いのですが、ショールームにはキッチンのスペシャリストである説明員もおり、一つずつ説明を受けながら判断することができます。
↑打合せ途中で使用したミニチュアモデル
クリナップに限らず、他のメーカーのショールームも静岡市にはたくさんあります。新築、リフォームの際には、必ず、ショールームの見学をすべきです。私どもがそのお手伝いをさせていただければと思います。
なお、当社はクリナップの「水まわり工房」登録店です。
ショールームを使ったフェアを行うこともあります。その時期が来ましたら、また、お知らせします。
クリナップ「水まわり工房」のホームページへリンク
(片桐秀夫)
2017年08月04日
ベッドを製作してみました。
先代の頃からお付き合いさせていただいている、老夫婦宅にて。
奥様が今までフローリングの部屋で布団を敷いて寝ていたのですが、足腰が弱ってきたこともあり、ベッドにしようとかと家具店を回ったのですが、希望するものが無かったそうです。
というのも、寝室としている部屋は4.5帖、この方の身長は145cmほど。市販の大きなベッドは部屋に納まりきれないし、身長から考えるともっとコンパクトで良いのです。
当初、ふとんが置けるだけの簡易的な台を想定していたのですが、出来上がったものはまさしくベッド。材料は積層板、胴縁等、建築業界で多く流通しているものを使用しています。パーティクルボードは使用していませんから、市販の家具よりも強度は十分あるでしょう。塗装も掛けませんでした。それでも、実用的には申し分なく、施主様には喜んでもらえました。全長165cmしかありませんが、これを使う人にとってはベストな寸法なのです。

大工さんの作るベッドなんて、あまり聞かないでしょう? こんなことが出来てしまうのは、やはり、当社が考える建築というものが、工場での大量生産ではなく、その時その時に対応する一品生産だからなのだと思います。それぞれの人に合った、最適な提案ができるように、これからも考えていきたいと思います。
(片桐秀夫)
奥様が今までフローリングの部屋で布団を敷いて寝ていたのですが、足腰が弱ってきたこともあり、ベッドにしようとかと家具店を回ったのですが、希望するものが無かったそうです。
というのも、寝室としている部屋は4.5帖、この方の身長は145cmほど。市販の大きなベッドは部屋に納まりきれないし、身長から考えるともっとコンパクトで良いのです。
当初、ふとんが置けるだけの簡易的な台を想定していたのですが、出来上がったものはまさしくベッド。材料は積層板、胴縁等、建築業界で多く流通しているものを使用しています。パーティクルボードは使用していませんから、市販の家具よりも強度は十分あるでしょう。塗装も掛けませんでした。それでも、実用的には申し分なく、施主様には喜んでもらえました。全長165cmしかありませんが、これを使う人にとってはベストな寸法なのです。
大工さんの作るベッドなんて、あまり聞かないでしょう? こんなことが出来てしまうのは、やはり、当社が考える建築というものが、工場での大量生産ではなく、その時その時に対応する一品生産だからなのだと思います。それぞれの人に合った、最適な提案ができるように、これからも考えていきたいと思います。
(片桐秀夫)
2017年07月28日
チラシ入れを新調しました
当社事務所の前にチラシ入れがあり、会社のPR誌などを置いています。
このチラシ入れはアクリル板でできている既製品なのですが、丁番の部分が弱く、劣化して壊れてしまいました。

そこで、新たなチラシ入れに交換しました。もっと安い製品もあるのですが、ある程度しっかりしたアクリルのものにしました。

新しいものは丁番の部分が改良されており、以前のものよりも耐久性に優れているようです。長い期間、耐えることができるよう、期待しています。

(片桐秀夫)
このチラシ入れはアクリル板でできている既製品なのですが、丁番の部分が弱く、劣化して壊れてしまいました。
そこで、新たなチラシ入れに交換しました。もっと安い製品もあるのですが、ある程度しっかりしたアクリルのものにしました。
新しいものは丁番の部分が改良されており、以前のものよりも耐久性に優れているようです。長い期間、耐えることができるよう、期待しています。
(片桐秀夫)
2017年05月12日
明日は 耐震補強現場見学会 です
明日、耐震補強工事現場見学会を予定しています。

↑上記画像をクリックすると、PDFデータのダウンロードができます。
ただ、明日の天気予報は雨・・・。
お足元の悪い中とは思いますが、興味のある方はお気軽にお越しください。
(片桐秀夫)

↑上記画像をクリックすると、PDFデータのダウンロードができます。
ただ、明日の天気予報は雨・・・。
お足元の悪い中とは思いますが、興味のある方はお気軽にお越しください。
(片桐秀夫)
2017年05月09日
TOUKAI-0のTwitterアカウントができたようです。
静岡県では、木造住宅の耐震補強プロジェクト「TOUKAI-0」について、さらに広く周知しようという趣旨で、
新たなTwitterアカウントを設定したそうです。
https://twitter.com/toukai_0?lang=ja
昨日、静岡県の担当者より「当社の耐震補強チラシを掲載させてほしい」と連絡がありました。
先ほど確認したら掲載されていました。耐震補強現場見学会としては栄えある1番目として掲載していただきました。
このアカウント、始めたばかりでフォロワーも今の段階で3名しかいませんが、これからいろいろな情報を発信していくとのこと。
興味のある方は、フォローしてみてください。
(片桐秀夫)
新たなTwitterアカウントを設定したそうです。
https://twitter.com/toukai_0?lang=ja
昨日、静岡県の担当者より「当社の耐震補強チラシを掲載させてほしい」と連絡がありました。
先ほど確認したら掲載されていました。耐震補強現場見学会としては栄えある1番目として掲載していただきました。
このアカウント、始めたばかりでフォロワーも今の段階で3名しかいませんが、これからいろいろな情報を発信していくとのこと。
興味のある方は、フォローしてみてください。
(片桐秀夫)
2017年04月28日
キーレスエントリーの電池交換
自分の乗ってるのはHONDA FREED SPIKEという車で、キーレスエントリーがついています。
車に向かって「ピッ」と押すとロックできるので、とても便利なのですが、最近、動作が鈍い。

この車に乗り出してから、5年くらい。電池交換を自分でやってみました。
ネジは1カ所だけ。しかし、堅くなっていて、回りにくいです。精密ドライバーのプラスで回そうとしたのですが、引っ掛かりが悪く、ネジ山をつぶしそう。雨の中でも使うことがあるわけで、ネジが少し錆気味のようです。マイナスの精密ドライバーで、回すのですが、これも結構大変。こういう時は、「押す力 8割、回す力2割」で回すと良いと聞いたことがありますので、そのように回したら、どうにかこうにか外れました。
ネジを外した後に、プラスチックのケースを開けたのですが、これも結構、難しい。でも、マイナスドライバーの先をくぼみにいれてこじ開けました。

プラスチックのケースの中には、さらに防水のケースが入っていて、それを開けると、リチウム電池が出てきました。

型番はCR1616という電池でした。100円ショップで買ってきて、早速交換。
ケースを閉める方は難なくできて、無事、交換は終了。試しに使ってみましたが、とても小気味よくロックの開閉ができるようになり快適になりました。
(片桐秀夫)
車に向かって「ピッ」と押すとロックできるので、とても便利なのですが、最近、動作が鈍い。
この車に乗り出してから、5年くらい。電池交換を自分でやってみました。
ネジは1カ所だけ。しかし、堅くなっていて、回りにくいです。精密ドライバーのプラスで回そうとしたのですが、引っ掛かりが悪く、ネジ山をつぶしそう。雨の中でも使うことがあるわけで、ネジが少し錆気味のようです。マイナスの精密ドライバーで、回すのですが、これも結構大変。こういう時は、「押す力 8割、回す力2割」で回すと良いと聞いたことがありますので、そのように回したら、どうにかこうにか外れました。
ネジを外した後に、プラスチックのケースを開けたのですが、これも結構、難しい。でも、マイナスドライバーの先をくぼみにいれてこじ開けました。
プラスチックのケースの中には、さらに防水のケースが入っていて、それを開けると、リチウム電池が出てきました。
型番はCR1616という電池でした。100円ショップで買ってきて、早速交換。
ケースを閉める方は難なくできて、無事、交換は終了。試しに使ってみましたが、とても小気味よくロックの開閉ができるようになり快適になりました。
(片桐秀夫)